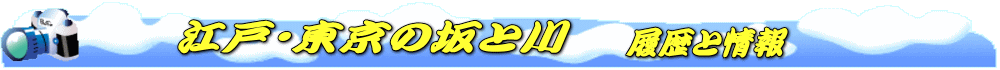
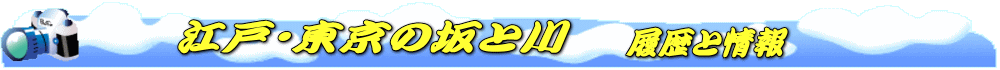
| Log(記録) | Logとは、このホームペイジを開設日から更新をかけたたびに更新日と簡単なコメントを記録していきます。このホームペイジの目的を完成させるために、目的場所に行き、写真に収め、編集し、更新するには、膨大な記録と、長い長い時間が必要です。いっぺんに記載するのは大変なことですので、目的を定め、歩きまわって、写真に収めた記録を、編集し、更新をかけていくやり方をとっていきたいと思います。それには、Blog的の更新をかけた日を、更新版としてこの”Log”の記録していきたいと思います。 |
| 05/25/2013 公開 |
このホームペイジは、”yeddo-aruki.b.la9.jp”として公開しています、以前のHP”journeyintoageofeddo"をベースに、”Google Earth”の機能を加え、より本格的な江戸探しを公開しているものです。ここに掲載されている写真に”journeyintoageofYeddo"と印してあるものはすべてこのホームペイジの製作者が自ら現地に行き、写真撮影したものですので、当然、著作権は、このホームペイジの製作者にあります。 |
| 06/01/2013 修正 | 各メーカーのPCにより表示状態が違うため、できる限り同じような表示となるよう一部修正した。 |
| 06/20/2013 更新 | 不具合店の修正と、港区北部の坂の項を公開 |
| 07/22/2013 更新 | 港区北部の坂道(1部、2部)を追加公開と、西久保八幡神社の石段坂道で小さな発見をしました。 |
| 08/30/2013 更新 | 港区西部(1部)を公開、麻布の七不思議、開発に埋もれた階段坂あり。 |
| 10/09/2013 更新 | 港区西部(2部)を公開 |
| 10/06/2013 更新 | 港区南部(1部、2部)を公開、忠臣蔵の赤穂浪士の史跡情報あり |
| 11/17/2013 更新 | 台東区(上野台地)を公開しました。 |
| 12/15/2013 更新 | 河骨側(春の小川)を公開しました。 |
| 02/28/2014 更新 | 文京区南東部(本郷・湯島)を公開しました。 |
| 03/18/2014 更新 | 文京区北部(千駄木・本駒込)の項を南東部の続きとして公開しました。 |
| 03/25/2014 更新 | 文京区南東部の項に菊坂とその横を流れていた水路について追加(文京区々役所行政情報センターより資料を入手)しました。 |
| 04/30/2014 更新 | 文京区その3:馬込・千駄木・小石川・千石あたりの坂道を文京区東南部の続きとして追加しました。 |
| 05/24/2014 更新 | 文京区の残り、西部を追加しました。 |
| 08/05/2014 更新 | 新宿区の内四谷・市谷・信濃町の坂道を公開しました。 |
| 18/11/2014 更新 | 新宿区全域を公開しました。 |
| 20/12/2014 更新 | 玉川上水から神田上水への助水路を公開と東大懐徳館にある湧水池(今は涸れ池)からの流れを追いかけ公開しました。 |
| 20/05/2015 更新 | 渋谷区の金王神社前を流れていた川、いもり川の流れを公開しました。 |
| 20/06/2015 更新 | 港区の根津美術館の東側にある坂道を”北坂”と称している坂が抜けていましたので追いかけてみましたが、なかなか面白い結果となりましたので独自の追跡と独自の検証で独立した項目として公開しました。 |
| 2015/10/12 更新 |
豊島区の坂道を追いかけました。この辺は豊島台地となっていてあまり坂道は多くありません。「今昔 東京の坂」では6個、豊島区発行の「豊島の坂」でも13しかありません。そのうち日無坂と下瀬坂は他区とまたがっていて他区でも取り上げられています。また13の坂以外に「坂学会」のホームページに載っていました宮坂・豊坂・銀鈴の坂等も載せてみました。また古くからの遺跡や神社が多くありそれらのいくつかも載せてみました。駒込日枝神社では駒込一丁目の町会長さんのお話を聞くことができ、また、大塚の天祖神社では面白いお話を聞くことが出来ました。 |
| 2015/10/12 更新 | |
| 2015/11/07 更新 |
豊島区の坂を捜し歩きました。この地域は江戸の外れとなり名のある坂はあまり多くはありませんが多くの史跡が残ると女ろではあります。現在に残る史跡を坂とともに捜し歩いても見ました。特に学習院大学目白キャンパス内に残る史跡には興味を覚え捜し歩いてみました。坂道の標はほとんどなく、豊島区が発行している(現在は絶版9「豊島の坂」がひとつの頼りでした。また坂のある地域は昼間あまり人通りもなく坂上から一方通行となり坂下でY字に分かれている道の不思議や、崖線いへばりついて造られている階段坂の由来等誰にも聞くことが出来ず、また区役所においても判らずでした。しかし豊島区の坂探しを始めたころが丁度秋祭りの準備期間中で日枝神社や天祖神社の関係者の方々にはいろいろと面白い話を聞くことが出来ました。 |
| 2016/02/28 更新 | 豊島区の坂道がうまくUPされていなかったので修正。その他の細かいところを修正しました。 |
| 2016/03/04 更新 | 川探しに豊島区の流れ跡図と弦巻川をUPしました。この川の流れにはいろいろなエピソゾがあり、大変おもしろい川跡探しになったと思います。 |
| 2016/08/28 更新 | 目黒区と区内のうち目黒駅周辺と中目黒駅周辺をUPしました。 03月にUPして以来私のPCにいろいろありまして、その間Microsoftで無償供給されていましたちょっとしてお絵かきソフトのPicasaが急に使えなくなってしまい、このアプリで編集している写真がすべて使用不可となってしまい、これに代わるアプリが無償で何かないかを探したり、Windows10が勝手にUPしだしたり、それに伴いいくつかのアプリケーション・プログラムのWindows10に対応版が必要となり四苦八苦して問題の解決に当たっていて坂探しどころではなかったのです。そのための費用や時間が必要となり、6月頃にやっと落ち着きが戻り、坂探しを再開しました。 ところが今度は私のHPのMemory容量が契約上限にかなり迫ってきてしまっているため考慮の末、”川探し”を別の方法でまとめることにし、このHPから外しました。何らかの形で”川探し”も継続していきたいと引き続き探し回っています。 |
| 2017/01/30 更新 | 今までUPした内容をCheckし、内容の簡素化を図りました。Memoryを大きく占めている写真や図形をできるだけ切り取ったり、整理したりして内容が変わらない程度に切り詰めてみました。また、”江戸の川”を併せて載せていましたが、契約Memoryの関係で、江戸の坂道を全部掲載できなくなりましたので、なにか方法が見つかるまで切り離しました。 |
| 編集後記:このホームペイジを制作するに当たり、現場に行ってその坂や川の景観をカメラに収めてはホームペイジの更新を行っていますが、いろいろな場所に行く度に、いろいろな方との出会いもあり、その中には面白い話や、書物にも載っていないような話が聞けたりします。また、現場に行ってみて、私自身が感じた何かを残しておけないものかを考えました。そこで、現場に行った時の素直に感じものを、この編集後記として書き表しておこうと考えました。同じ場所に何度も足を運びながらも目的が見つからなかった時や、探し回ってやっと見つけた時の気持ち等を思ったそのままに書き表していこうと思います。 | |||||
| 2013年10月08日: |
港区の今に残る名のある坂道を掲載することが出来ました。港区の坂道を歩いての感想は、港区は本当に傾斜の多い地域であるということが深い印象です。北は千代田区から続く台地があり、中央を古川が流れ台地を南北に分断しています。南は麻布台地の先端に当たり半島状の台地が続いています。地形歩きとしてはとても興味の尽きない地域でもあります。また多くの大名の下屋敷が置かれていた地域でもあり、西郷隆盛と勝海舟の江戸城開城の会見の薩摩藩の下屋敷があったり、忠臣蔵で有名な四十七士のお墓のある泉岳寺や大石内蔵助らが一時預かりとなりその後切腹した大名屋敷跡の切腹の場と歴史的にも多くの史跡が残っています。 | ||||
| 2013年10月20日: |
上野台地を歩いていた時のエピソードが2つありますので紹介します。ひとつは蛍坂から築坂と歩いていて三崎坂に出た時の体験ですが、三崎坂に出て古い地図を片手にその場所を確認していたところ三崎坂と築坂からの道がある角に”三崎坂”と言うカフェがあり、その店先に座っていた若い女性の方が”なにかお探しですが?”と尋ねてきました。ここがどこかを確認していることを伝えたところ店先にあった絵地図を持ってきてその場所だけではなく周りの道案内もしてくれました。この三崎坂商店街の方だそうで商店街の活性化を推進しているとのことでっても親切に教えてくれました。 もうひとつは、善光寺坂途中を坂上から見て左折すると三段坂、清水坂方向に出ますが、丁度三段坂上のT字路の突き当りにあるお店屋さん(界隈の絵地図や観光物を販売しています。)に行って”まちあるきマップ 谷中、根津、千駄木”を購入したところ、お店をきりもりしていたとても品のいい女性の方が丁寧にこの界隈のいろいろなことを話してくださいました。そのひとつとして、このお店の隣に今な使われていませんが小さな小さな郵便局の建物がありました。この郵便局はこの方のお父さんが”この界隈には郵便局がなくて不便だ。”と言って区(その頃は何と言っていたか?)に願い出てすべて自費で郵便局の建物を建てたそうです。その建物は今は使われていませんがこのお店の隣に残っています。 |
||||
| 2013年12月15日: |
「春の小川」の童謡歌に歌われた河骨川をその水源地から宇田川に合流するまでを公開しました。何回となく流れ跡を追跡してみましたがその度に近隣に住まわれている方々にお会いできお話を聞くことが出来ました。道に迷ってきょろきょろしていると通りすがりの方が声をかけてくださったり、とても親切に道案内してくださったりしていただきこの回だけではありませんが、私くらいの年齢の方やもうすこし高齢の方々が戦後の昭和期を懐かしんでおられる方が大変多くおられるということが判りました。私もそのひとりですが現在あまりにも世の中が発展してしまって日本人が本来持っていた大切なものが失われてしまった。と痛感します。それは人と人との結びつきです。現在はその人と人の結びつきがとても希薄に感じます。 |
||||
| 2014年02月28日 |
今年から文京区に入りました。文京区は非常に坂の多い地域で「文京区 観光ガイド」や「文京区の坂道」には合計115の坂道が記されています。今回はそのはじめとして本郷・湯島の坂を探索しました。南東部は本郷台地の終りの地でもあり、非常に狭い地域に多くの坂道が存在します。地形的にも複雑な入り組がありとても興味のある地域です。おもしろいのはほぼ東西に走る幹線道路に沿っていくつもの坂が存在しています。特に興味をそそられたのは”菊坂”と”下道”とその周辺です。昔々この辺は谷地が奥深く切り込んでいたとても興味のある地形をしています。その低地付近に明治時代の有名な方々が居を構えていたこともあり地図を片手に歩いているグループの方々も多く見かけました。また、とてつもなく広大な大名屋敷があったり、この周辺にお住いの方々には言葉は悪いですが、鐙坂周辺のようにとても狭い急傾斜の地形にも多くの方々が住んでいることも興味の湧く地形です。 |
||||
| 2014年03月25日 |
文京区の坂道を捜し歩いているうちに巻石通りを歩いていた時に金富小学校の外れに神田上水の経路図板が立っていました。神田上水が大洗取水堰からどのような経路で今の小石川後楽園を経由して、水道橋近くにあった神田川を横切る掛樋までが簡略的に描かれていました。また、その当時の状況が書かれている資料を探しに文京区々役所の行政情報センターにお伺いしましたところ、今は販売されていませんが、文京区教育委員会が発行した資料の添付に当時の様子と現在を重ね合わせた地図がありました。許可を得て必要な部分をコピーさせていただきましたが、家に帰りよく見てみましたところ薄透けてよく見えませんでしたが菊坂とその周辺がありました。”Paint
Shop”というユーティリティで少し編集しましたところまあまあ判別ができるようになりましたので”菊坂”の特集のところに追加してみましたのでご一見いただければと思いUPしてみました。 |
||||
| 2014年04月30日 |
文京区の東南部を3つに分けて更新しました。この辺は小石川台地と白山台地とに挟まれた谷地や小石川台地に沿った崖線が連なっておりとても坂道の多いところでもあります。坂道探しも一回ではなく同じく区域を何回も何回も歩きました。そのたびに新しい発見や変わった景色を見つけることができ地形好きには大変興味を抱かせる地域でもあります。また、白山台地と小石川台地の間を千川(小石川)が流れた後にある千川通りや、小石川台地の反対側に位置する神田上水跡がある巻石通りがあり、坂道とは別にまた興味の尽きない地域です。千川上水や神田上水については、”川探し”で詳しく追って行こうと思いますが、これら台地と低地を流れていた川はお互いに切っても切れない関係が成り立っていたことがよく判ります。それらの地形をうまく利用して生活していたのが江戸時代ではなかってでしょうか。 |
||||
| 2014年05月25日 |
文京区の残り部分、西部地域の坂道をUPしました。これで一応文京区全体の坂道を載せたつもりです。文京区の多くの坂道を歩き回っていろいろな方々とお話したり、お住まいの周りの情報を教えていただいたり、また訪れたタイミング、タイミングで大雪の後だったり、桜の季節で御花見客でにぎわっていてなかなか景色のみの写真にならなかったり、偶然にも切支丹屋敷跡の遺跡発掘調査を目撃したり、小石川後楽園を訪れた時には丁度池や滝の水を抜いて池やその流れの調査をしている現場に遭遇したり、近くに交番のある坂道が多くあり、お巡りさんと立ち話をしたりで思わぬ偶然に多くであいました。また、資料や情報を得に何回も訪問した区役所の方々には一方ならぬお世話になりいろいろなお話をいただいたり、情報や資料を紹介していただきました。皆様とても親切で心から感謝です。 |
||||
| 2014年07月10日 |
新宿区の坂道から ”Google Earth” で表示される等高線を目安に坂上と坂下の標高とその差(標高差)をおおよそですが坂名の横に表示してみました(すでに作成した区の坂道にも随時対応していきます。)。それにより掲載されている坂がどれくらいの傾斜を持った坂道であるのかが推察できると思います。しかしながら坂道の坂上と坂下の距離をどのようにして知るか?実際に坂道を巻尺等で測ればよいのですが、個人で測るには実際的に不可能と思います(車が通ったり人の歩行を邪魔しあり、物が置いてあり直線が確保できない、等たくさんの問題があります。)。国土地理院や地図の出版会社、等ではそれに近いものがありますが、坂道に限ってとなると見つかっていません。またj個人が開設している坂道を扱っているホームペイジの中にはそれに近いものも見られますが、大変失礼ですが、坂が一定の傾斜ではないことをどのように表しているかが判りません。その坂道の示す坂の長さが判るとその坂の持つ坂上の角度と坂下からの角度が計算できますのでどれくらいの角度(傾斜)を持った坂なのかがより理解できると思いますが、今はその方法を模索中です。そこで大きな問題として昔からの坂道は単に直線坂が少なく、そのほとんどが途中で曲がリくねっていたり、坂がうねっていたりして一定の角度を持った坂道ではないと言うことです。何年先のことから判りませんが、それらがすべて判る坂道の3DCGの作成までこぎ着ければいいなと考えています。 |
||||
| 2014年08月05日 | 新宿区の内、四谷・市谷・信濃町の坂道を追いかけました。 |
||||
| 2014年09〜11月 |
新宿区の残りの地域にある坂道を追いかけてみました。偏見ですが新宿と言えば繁華街や超高層ビル群ばかりしか目にしていなかった私にとっては驚きと感激の連続の坂道探し歩きでした。新宿区域を歩いた感想としては”新宿区はこんなにも凸凹なんだ!”と言うことです。歩けば歩くほど多くの坂道とそれにまつわる色いろんな話を新宿区役所の担当の方々やその地域にお住いの方々等たくさんの方々から坂道に関するお話やその周りの地域に関するお話を大変多く聞かせていただきました。昔からその地域にお住いの方々にとっては安住の地であり昔からの言い伝えや昔話、地域の謂れ、等を持った方々が大変多く住んでおられます。しかしそれらの方々のお話は断片的であったり、非常に小さな範囲のお話であったり、その方々がお持ちの情報は非常に小さなものです。しかしながらそれらの情報は昔を顧みない現代人にとってはとても貴重なものであると思います。それらの情報がなくなってしまわないうちになんとか形に出来ないものかと苦慮しています。 |
||||
| 2014年11月18日 |
新宿区全体をUPしました。かなり多くの時間をかけて坂以外にも興味のわいた事柄を追いかけてしまいましたがそれなりに新宿区を言う地域の今までは全く知らなかった土地柄やいろいろな歴史やそれにかかわっていた人たちも少しですが知ることができました。新宿区は区史がとてもよく整理されており少しでも疑問に思った事柄を調べに新宿区役所に数多くお伺いし担当者の方々からもいろいろな事柄を教えていただいたり観光地図には載っていない坂やその歴史などもお伺いするk徒ができました。今までお伺いした区役所はどこでも同じですがお伺いするたびに変な質問やごくごく興味本位の質問などにも大変親切に応対していただき感謝感謝の一言です。 | ||||
| 2014年12月20日 |
玉川上水から神田上水への助水路があることが判り追いかけてみました。助水路跡は小さな公園になっていたり細い曲がりくねった路地道となっていたりしていました。 また、文京区の東京大学敷地内「懐徳館」にある池から流れ出ていた湧水が菊坂脇を走る下道を流れていたことを見つけ追いかけました。この流れは白山通り横を流れていた東大下水に流れ込んでいたとの資料が多くあり、またその流れは白山通り手前で西片方面の谷地の億止まり辺りから流れていた湧水とが合流していたことも判り追いかけました。この流れの情報は文京区資料室の担当の方のお話でより多くのことを知ることができ容易に追いかけることができました。 どのこ区役所の担当者の方々もそうですが、訪ねていくと大変親切丁寧に教えていただき、またそれに関する資料等も見せていただいたり、教えていただき私のホームペイジ制作に大変に役立っています。大変感謝感謝です。 |
||||
| 2015年06月20日 |
渋谷区にある金王神社前を流れていた川といもり川を源流と思われれる場所から追跡しました。 金王神社前の流れを追いかけていた時には、金王神社の方からその川と川に架かっていた石橋の映っている写真のコピーをいただき(本文内参照)、川と石橋に係わるお話や現在も残っている石橋の石を案内していただきました。また、源流から流れを追いかけていた時に、以前”黒鍬谷”と呼ばれていた付近にお住いのお年寄りから、戦前から戦後にかけての黒鍬谷の様子などをお聞きすることができました。 |
||||
| 2015年10月12日 |
大塚駅すぐの日枝神社に2度目にお伺いしたところ、丁度秋祭りの季節でその準備をしておられる方がおられましたのでこの近辺のお話をお伺いしようとしたところ丁度駒込一丁目の町会長さんがおられていて紹介されました。町会長さんのお話では、この日枝神社は位置的に朝日をとてもきれいに見ることが出来たことや、境内社として祀られている稲荷のお狐様の目が他社のお狐様と違って鋭いこと、稲荷様の横には明和二年(1765)と彫られた手水があり、そのすぐそばには雷に打たれても(幹が裂けて黒く焼けている。)生き続けている銀杏の木などを紹介していただき、宮司さんの書かれた数枚の説明書もいただくこと打撃ました。また大塚の天祖神社ではやはり秋祭りの準備をされていた宮司さんのいろいろなお話の中で興味を引いたのは、”昔江戸と言われた地域は天祖様の右掌で守られている。”と言うお話です。なるほど地形図をよく見てみますと東京都市部台地は右手の手のひらの形をしていると見えなくもありません。昔の人たちはそんなことから信仰をしているのだなぁ。と納得もしました。 | ||||
| 2016年2月28日 |
昨年のUPから大変に間隔があいてしまいましたが、豊島区の坂道を探して歩いていましたところ、豊島区から文京区にかけて流れていた2つの川跡(弦巻川・水窪川)やそれに関する周りの歴史(音羽町の紙漉き/音羽の滝/旧マレーシア大使館跡/鏡ヶ池会館/等)がとても気になりそちらに多くの時間を割いてしまっています。ですが大変に面白い川歩きとなっています。誠意編集をかけています。とても面白い興味の湧く内容となっています。また、それらのからむエピソードなども多数盛り込んでいますのでご期待ください。 | ||||
| 2016年3月4日 | やっと豊島区の大きな流れの中、弦巻川の編集が終わり、UPしました。この川跡を探すために何度となく川の流れ跡の地域を訪れました。その度にいろいろな方とお会いし、会話をすることが出来ました。ある日、音羽が滝のあったとされる場所を探しに旧西青柳町の高台をうろついていた時に目の不自由な青年に出会い、地下鉄の護国寺駅までの短い間でしたが会話を楽しむことが出来ました。みな一期一会でしたが、とても心休まる楽しいひと時でした。 | ||||
| 2016年7月31日 | 読者の皆様にはWindows10の問題はいかがなされていますか?私は無償期限ぎりぎりでUPしましたが、案の定使っていたいくつかのUtility
Programが対応できなくなり、最終的には対応版を購入せざるを得ませんでした。これってUserには大変な苦労と出費ですよね。 8月から本来の坂探し、川探しに戻ります。 |
||||