| |
 |
| |
ここからは文京区の西部を歩いてみました。 西部全体を表現しますとその範囲が広く(開運坂が飛びぬけて北に位置している。)一枚の地形図で表しますと図が小さくなりすぎて見にくくなってしまうため2つに分けてみました。第一部は西部の南の部分、二部はその残りの上側(北側)としてみました。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
第一部は小日向台地からと目白台地から音羽通りへと下っていく坂道と文京区の最西部新宿区や豊島区との境までの坂道を追いかけます。 |
| |
鷲坂、八幡坂、鼠坂、 目白坂、新坂、七丁目坂、鳥尾坂、鉄砲坂、日無坂、小布施坂、豊坂、幽霊坂、胸突坂(水神坂)、
希望の坂、三丁目坂、付属校坂、富士見坂、開運坂、小篠坂、清戸坂、幽霊坂(遊霊坂)、薬罐坂、 |
| |
 |
| |
ここからは文京区の坂道の最後の部分、文京区西部の坂道を追いかけます。この部分は南側は神田川が流れ、東側は半島状の台地((目白台地)がを形成されていて、音羽通りを挟んだ反対側は小日向台地と呼ばれる台地が形成され音羽通りが通る低地が深く豊島区内まで入り込んでいます。その分坂道も多いようです。以前タモリさんのテレビ番組で取り上げられましたが、この半島状の先端近くに”椿山荘”があり、この半島状の地域まで海が入り込んでいて、太古の昔にここに人が集落を造って生活していた遺跡もあると紹介されていましたようにかなり地形が入り込んでいて歩きがいのある地域でもあります。また、この狭い地域の極近くに幽霊坂が2ヵ所あります。なぜそんな近くに同じ名前の坂が2つもあるのかも探りながらの坂道探しとなりました。また上の陰影図に昔の道をロール・オーバーしてみました。これらを比較して見ますと現在に残る坂道がほぼ昔のままであることが判ります。 |
| |
鷺坂 (さぎさか) |
| |
鷺坂上 |
鷺坂中 |
鷺坂下 |
| |
この坂の標には『この坂上の高台は、徳川幕府の老中職をつとめた旧関宿藩主・久世大和守の下屋敷のあったところである。そのため地元の人は「久世山」と呼んで今もなじんでいる。この久世山も大正以降住宅地となり、堀口大学(詩人・仏文学者 1892−19821)やその父で外交官の堀口九万一(くまいち)(号長城)も居住した。この堀口大学や、近くに住んでいた詩人の三好達治、佐藤春夫らによって山城国の久世の鷺坂と結びつけた「鷺坂」という坂名が、自然な響きをもって世人に受け入れられてきた。足元の石碑は、久世山会が昭和7年7月に建てたもので、揮毫は堀口九万一のよる。一面には万葉集からの引用で、他面にはその読み下しで「山城の久世の鷺坂神代より春ハ張りつつ秋は散りけり」とある。文学愛好者になる「昭和の坂名」として異色な坂名といえる。』と書かれています。坂は江戸川橋から目白通りを少し上った右側にあり、反対側には目白坂があります。細い脇道ののような道を入りと鷺坂が見え、坂中で直角に折れ曲がっていて傾斜もきつく車も通らないような細い坂道です。山の斜面を切り通して造られた坂道であることが容易に判る道でもあります。ご覧のように高い石塀に囲まれた景観からきっとその昔は”昼なお暗き”坂道であったのではと想像します。坂中にある「鷺坂」の石碑の両横面にはなにやら文字が刻まれていますが「山城久世の鷺坂 神代・・・・」と読めましたが日光の加減かすり減っているのかあとは判読できませんでした。小日向台地から音羽通りへくの字に降りてくる坂道です。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
八幡坂 |
| |
八幡坂上 |
八幡坂中 |
八幡坂下 |
| |
この坂の標には『「八幡坂は小日向台三丁目より屈折して、今宮神社の傍に下る坂をいふ。安政四年(1857)の切絵図にも八幡坂とあり。」と、東京名所図会にある。明治時代の初めまで、現在の今宮神社の地に田中八幡宮があったので、八幡坂と呼ばれた。坂上の高台一帯は「久世山」といわれ、かつて下総関宿藩主久世氏の屋敷があった所である。』と書かれています。坂は鷺坂と同じく小日向台地から音羽通りへと下っています。説明の通り高台より非常に角度のある傾斜を持って下っている坂道で坂途中で直角に右に曲がっている階段坂でもあります。坂上には車が通れないような仕切りがあり、こんな坂道は車は通れないな!としばらく坂道上からの台地下の景観を眺めていましたとこと、郵便配達の自動二輪者車が階段横の平らな部分を駆け下りていきました。”地元の人たちは慣れっこになっているのかな?”とおもいつつ眺めていました。台地上から音羽通りへの傾斜がよく判る坂道でもあり、その昔はきっとすばらしい景観がみられてのではないでしょうか?そんな思いにふけってしまう坂道でもありました。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
鼠坂 (ねずみさか) |
| |
鼠坂上 |
鼠坂下 |
この坂の標には『音羽の谷から小日向台地へ上がる急坂である。鼠坂の名の由来については「御府内備考」には「鼠坂は音羽五丁目より新屋敷へ上る坂なり、至ってほそき坂なれば鼠穴などいふ地名の類にてかくいふなるべし。」とある。森鴎外は「小日向から音羽へ降りる鼠坂と云ふ坂がある。鼠でなくては上がり降りが出来ないと云ふ意味で附けた名ださうだ・・・人力車に乗って降りられないのは勿論、空車にて挽かせて降りることも出来ない。車を降りて徒歩で降りることさへ、雨上がりなんぞにはむづかしい・・・」と小説「鼠坂」でこの坂を描写している。また、”水見坂”とも呼ばれていたという。この坂上からは、音羽谷を高速道路に沿って流れていた、弦巻川の水流が眺められたからである。』と書かれています。坂は説明の通り非常に急傾斜の細い階段坂で上り下りには息がきれそうな坂道です。
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
目白坂 (別名:不動坂) |
| |
目白坂上 |
目白坂中 |
目白坂下 |
| |
この坂の標には『西方清戸(清瀬市内)から練馬経由で江戸川橋北詰にぬける道筋を「清戸道」といった。主として農作物を運ぶ清戸道には目白台地の背を通り、このあたりから音羽谷の底地へ急傾斜で下るようになる。この坂の南面に、元和4年(1618)大和長谷寺の能化秀算僧正再興による新長谷寺があり本尊を目白不動尊と称した。そもその三代将軍家光が特に「目白」の号を授けたことに由来するとある。坂名はこれによって名付けられた。「御府内備考」には「目白不動の脇なれば名とす」とある。かつては江戸時代「時の鐘」の寺として寛永寺の鐘とともに庶民に親しまれた寺も明治とともに衰徴し、不動尊は豊島区金乗院にまつられている。』と書かれています。坂は、坂上は今の目白通りに合流し坂上付近には椿山荘の大きな入口があります。そのなだらかな道を少し下っていきますと傾斜がどっときつくなり大きく左にカーブしながら、またゆっくりとS字にカーブしながら目白通りに出ます。音羽通りを挟んで反対側は”巻石通り”となりその昔の主要な通り道であったのでしょうが、今は新しい目白通りの抜け道的な間道となってしまっています。音羽の低地から小日向台地上までかなりの高低差があり、その昔はきった行きかう人たちにとって眺めのいい坂道であったと思われます。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
新坂 (目白新坂、椿坂) |
| |
目白新坂上 |
目白新坂下 |
この坂の標には『この坂の南にある目白坂のいわばバイパスとして、明治二十年代の半ば頃新しくつくられた坂で古い目白坂に対して目白新坂という。明治末期に書かれた「新選東京名所図会」によると、「音羽八丁目と同九丁目の間より西の方関口台町へ上がる坂あり椿坂という、近年開創する所、坂名椿山の旧跡に因むなり、俗名又新坂ともいへり、道幅広く、傾斜緩なり。」とあり、椿坂、新坂ともいう。』と書かれています。坂は目白通りにあり坂上は椿山荘正面少し上で目白坂が合流しています。道は清瀬市から続き江戸川橋に続く主要な道路であり、目白坂のある道に比べ真っ直ぐに江戸川橋方向へ傾斜も緩やかに道幅も広く立派なt道路となって下っています。目白坂のある道の不便さからでしょう、明治半ばに開発された新しい坂道です。長い長い坂道ですが近代的な道でもありあまり興味のわかない坂道でもあります。
坂中にある銅版の説明書きが風雨に晒されて錆びてしまい読みにくくまた、傾いてしまっていました。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
七丁目坂 |
| |
七丁目坂上 |
七丁目坂中 |
七丁目坂中 |
| |
七丁目坂下 |
説明版があったと思われる |
この坂の標は見当たりませんでした。しかし坂途中の民家のブロック塀に写真左のような坂の説明版が埋め込まれていたと思われる跡がありましたのであえて掲載しました。(文京区々役所で確認ですね。)
坂は民家の間を通る細い道にある手すりのついた急傾斜の階段坂です。坂上はなだらかで左に曲がったところ(写真上中)から急激に落ち込んで音羽通りへとでます。この坂は「今昔 東京の坂」には載っていませんが、文京区の「観光ガイド」マップにありましたので探しに行きました。坂上にはバイクが通れないようになっていて、手すりがついた急激な角度を持つ階段坂です。坂中からはその傾斜も少し緩やかになっているまったくの生活道路にある坂道です。
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
鳥尾坂 |
| |
鳥尾坂上 |
鳥尾坂下 |
鳥尾坂下にある石碑 |
| |
この坂の標には『この坂は直線的なかなり広い坂道である。坂上の左側は独協学園、右側は東京カテドラル聖マリア大聖堂である。明治になって、旧関口町192番地に鳥尾小弥太(陸軍軍人、貴族院議員、子爵)が住んでいた。西側の鉄砲坂は人力車にても自動車にても急坂すぎたので、鳥尾家は私財を投じて坂道を開いた。地元の人々は鳥尾家に感謝して「鳥尾坂」と名づけ、坂下の左わきに坂名を刻んだ石柱を建てた。』と書かれています。坂は車も通れる急坂で徒歩での上り下りにはかなりの体力を必要とします。坂上には学校があり体育系の生徒がこの坂を駆け足で上下しトレーニングに励んでいました。説明文からこの坂も明治以降に造られた坂道のようです。それにしてもこの辺一帯の坂道はみな急坂ばかりです。この坂道も「今昔 東京の坂」には載っていませんが、文京区の「観光ガイド」マップには載っていました。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
鉄砲坂 |
| |
鉄砲坂上 |
鉄砲坂中 |
鉄砲坂中 |
| |
鉄砲坂下 |
 |
この坂の標には『この坂は音羽の谷と目白台を結ぶ坂である。坂下の東京音楽大学学生寮あたりは、江戸時代には崖を利用して鉄砲の射撃訓練をした的場(角場・大筒角場ともいわれた。)であった。その近くの坂ということで「鉄砲坂」とよばれるようにあった。』と書かれています。坂は坂上ははじめゆったりとした傾斜であり大きく右にゆっくりと曲がり、その先から急激にかなりの傾斜を持って落ち込んで音羽通りに出ます。説明板には江戸時代のこの辺の地図も載っており坂下すぐ横に”的場”(左の写真赤い丸の中)も書かれています。この坂道は旧目白通りと音羽通りを結ぶ要の道でもあったと思います。(左の写真の江戸時代のこの辺の地図は「江戸切絵図集成:尾張屋版」から写したものと思われます。)
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
日無坂(別名:東坂、富士見坂) |
| |
日無坂上 |
日無坂中 |
日無坂下 |
| |
この坂の標は見つかりませんでした。文京区の「観光ガイド」マップを片手にこの辺を訪れた時、この坂上には容易に辿り着いたのですが坂道の景観から見て上左の写真の右側にまっすぐ伸びている坂道が”日無坂”と思い込んでしまいそちらを下って行きましたところ坂途中に”富士見坂”の碑が立っていました。上り下りをすること2回、あまりの坂道の傾斜にへこたれて道端に腰を下ろして休んでいたところご近所の方なのか話しかけてこられて日無坂”を探していることを告げたところ、”このへんはもう豊島区だよ!”と教えてくれました。もう一回その坂道を下ったところにあった住所表示も豊島区になっていました。文京区の「観光ガイド」マップを詳しく見てみましたところなんと坂上の左側の細道が”日無坂”であることを確認(私の見間違え、勘違いでした。)、もう一回坂上に行って上にある写真を撮りながら下ってみました。この坂は文京区と豊島区の区境に日無坂は文京区に入り、そのすぐ右横の建物は豊島区となるようです。坂は目白通りから脇道のようなごく細い道を神田川方向に下っていく非常に険しい急傾斜の坂道です。坂上からは神田川沿いの低地を一望することができ、その昔はきっと富士山も見えたのではないでしょうか?そんな気がする非常に高低差の激しい坂道です。また文京区側の”日無坂”と豊島区になる”富士見坂”との間にある坂上にとんがった三角形の土地に建つ家にも興味を持ちました。急傾斜に沿って崖をうまく利用して建っています。大変興味のある景観です。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
小布施坂 |
| |
小布施坂上 |
小布施坂中 |
小布施坂下 |
| |
この坂の標には『江戸時代、鳥羽藩主稲垣摂津守の下屋敷と、その西にあった岩槻藩主大岡主膳正の下屋敷の境の野良道を、宝暦11年(1761)に新道として開いた。その道がこの坂である。坂の名は、明治時代に株式の仲買で財をなした小布施新三郎という人の屋敷がこのあたり一帯にあったので、この人の名がとられた。古い坂であるが、その名は明治のものである。』と書かれています。坂は目白通りから下ってくる途中の傾斜もある極細く長い坂道です。坂上から見て左側には”日本女子大学付属豊明小学校”があり開けていますが、坂道自身は両側に昭和の面影を残す人もあまり通らない坂道です。坂下には「観光ガイド」マップにも載っています”豊川浴場”があります(坂下の写真左の建物)。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
豊坂(とよさかと読む) |
| |
豊坂上 |
豊坂中 |
豊坂下 |
| |
この坂の標には『坂の名は、坂下に豊川稲荷社があることから名づけられた。江戸期この一帯は、大岡主膳正の下屋敷で明治になって開発された坂である。坂を下ると神田川にかかる豊橋があり、坂を上がると日本女子大学前に出る。目白台に住んだ大町桂月は「東京遊行記」に明治末期このあたりの路上風景を、次のように邊?(擦れて読めず。)べている。「目白台上れは、女子大学校程近し、さきに早稲田大学の辺りを通りける時、路上の行人はほとんど皆男の学生なりしが、ここでは海老茶袴をつけたる女学生ぞろぞろ来るをみるにつけ、云々」 坂下の神田川は井の頭池に源を発し、途中、善福寺川、妙正寺川を合わせて、流量をまし、区の南辺を経て、隅田川へ注いでいる。江戸時代、今の大滝橋あたりに大洗堰を築いて分水し、小日向台地の下を素掘りで通し、江戸市民の飲料水とした。これが神田上水である。』と書かれています。坂は、目白台上を通る目白通りから片道一車線の道幅でかなりの角度を持って下り、坂途中では左にカーブしし坂下でまた曲がりくねった傾斜のある坂道です。時代的に新しい坂のようで坂上目白通りの反対側には”幽霊坂(遊霊坂)”から”清戸坂”に出ることができます。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
幽霊坂 |
| |
幽霊坂上 |
幽霊坂中 |
幽霊坂下 |
| |
この坂の標は見つかりませんでした。また、「今昔 東京の坂」には載っていません。が、文京区が配布している「観光ガイド」マップには目白台地上にある”目白台運動場”と”旧細川候邸和敬塾本館”の間を抜ける細い細い両側を高い塀に囲まれ背の高い木々が生い茂る”昼なお暗き”夜になるとその名の通り何かが出てきそうな感じの坂道です。坂は目白通りからの細い平坦な道を少し歩き途中から急激に落ち込んでいるコンクリート道ですが、自転車を通さないように坂下にはご覧のような柵がある傾斜のきつい坂道です。いつごろからある坂道なのでしょうか、坂下左近くには”新江戸川公園”があります。坂上の目白通りを目白台運動公園を過ぎ日本女子大のバス停近くから清戸坂に抜ける坂道があり、その坂道にも幽霊坂の名が付いた坂道がありますが、幽霊という感じではこちらの坂道の方が格段にその名にふさわしい感じのする坂道です。 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
胸突坂(別名:水神坂) |
| |
胸突坂上 |
胸突坂中 |
胸突坂下 |
| |
この坂の標には『目白通りから蕉雨園(もと田中光顕(みつあき)旧邸)と永青文庫(旧細川下屋敷跡)の間を神田川の駒塚橋に下る急な坂である。坂下の西には水神社(神田上水の守護神)があるので、別名「水神坂」ともいわれる。東は関口芭蕉庵である。坂がけわしく、自分の胸を突くようにしなければ上れないことから、急な坂には江戸の人がよくつけた名前である。ぬかるんだ雨の日や凍りついた冬の日に上り下りした往時の人々の苦労がしのばれる。』と書かれています。坂上から左側はブロック塀が続き、坂下左には”関口芭蕉庵”があり、ここもうっそうとした木々に挟まれた大変角度のある急激な階段坂です。坂に階段や坂中央に手すりを設けなければならないほどの急な傾斜を持つ坂道です。ここもその時代には坂上からは眺めの良かった場所ではないかと思われます。また、坂下右側には小さな社を持つ神田上水の守護神を祀る”水神社”があり社前には杉?の巨木が二本真っ直ぐに立っています。訪れた日は晴れた日の西日の強い日で、社内の水神を祀る”銅鏡”が祀られているのを金網越しに見ることができました。 |
| |
 江戸切絵図 江戸切絵図  |
| |
ここでこの辺の坂道を「江戸切絵図集成」から尋ねてみたいと思います。 |
| |
 |
| |
 江戸切絵図集成:尾張屋版「音羽繪圖」 江戸切絵図集成:尾張屋版「音羽繪圖」 |
| |
上の地形図のロール・オーバー図はこの地域の今に残る坂道と「江戸切絵図集成」に描かれている道を現代の道に出来る限り合わせてトレースしてみた図です。一部八幡坂と鼠坂の間の道の本数や旧目白坂側の目白通りと音羽通りと護国寺前を通り不忍通りに囲まれた大きな三角地帯の道が道のずれや本数の違いがありうまく表せていませんが切絵図の時代の道はほぼこのような道筋であったと思います。新旧の道筋を重ね合わせながら坂道の新旧比較をしていきたいと思います。また下の切絵図の「音羽繪圖」はこの部分を国会図書館にてコピーを入手し掲載してみました。この「切絵図」の方が道筋を追うにはよく判るのではと思います。 |
| |
切絵図の真ん中には江戸川橋から真っ直ぐに護国寺まで伸びる”音羽通り”があります。江戸川橋からひとつ右側にある曲がりくねった道が”大日坂”のある道です。今でも同じ位置にあります。その上(北側)には音羽通りから一本隔てて目白通りの向かい側にT字路になっている道がありこれが”鷺坂”のある道と思われますが坂中から左折しそのまま行きますと”行き止まり”となっています。その上(北側)には”八幡坂”と書かれたこれも直角に曲がっている道があり今と変わりはないようです。八幡坂の坂上をそのまま進んでいきますと”鼠坂(子ツミサカ:と書かれている。)”に突き当ります。しかし鼠坂の坂下は今のように真っ直ぐではなく、坂下で鉤型に折れ、音羽通りに出ています。この八幡坂と大日坂の道との間にある鼠坂までの間には”御賄組”と書かれた土地が幾筋かの道に分かれてこの地域を占有しています(江戸時代のお城の賄い方(炊事係)の人たちの住居が密集していたようです。)。八幡坂と鼠坂までの間にある道の本数は違いますがこの形状はほぼその頃と変わっていないようです。鼠坂の上(北側)は”安藤長門守”の広大な屋敷やその他の大名の屋敷(敷地はそんなに大きくない。)があり道はありません。今もこの辺は鼠坂北側には”筑波大学付属中・高校”その上には”お茶の水女子大学”の複合施設があり今も道は”付属横坂”のある道だけがあります。ひとつ興味のあることはこの音羽通りの東側(右側)に沿って護国寺方面よりひと筋の川(人工?)か下水道なのかは確かではありませんが、流れが青色で書かれていて、神田上水に流れ込んでいます。音羽通りの両側は音羽町壹丁目から九丁目までの門前町の様子があり町人が住んでいようですが、その通りを外れると大名屋敷や武家屋敷が密集しています。目を音羽通りの左側(西部)に移してみますと神田川すぐ上に”旧目白通り”があり江戸川橋をすぐ上がったところから”目白坂”があります。今の目白新坂はなくその昔は目白台地と呼ばれる台地上を江戸川橋付近くから上がり道を真っ直ぐに埼玉県方向に延びている主要な道であったと推察できます。この目白通りから上(北側)には”鉄砲坂”までの間はひと筋の道しか音羽通りと目白通りお結んでおらず、これが”鳥尾坂”のある道と思ったのですが”鳥尾坂”の説明では明治以降に造られた道とのことで相当する道が見つかりませんでした。蓮光寺がこのころからありその道は蓮光寺前を通っています、蓮光寺が現存するのでその前の通りを見てみましたが絵図のような道筋はなく、この辺は大変変わってしまっていると思われます。その上(北側)には道が音羽通りから”薬罐坂”からの道に交わっていますが、それが今の”三丁目坂”のある道ではないかと思われます。”鉄砲坂”の道と”三丁目坂”の道の間は武家屋敷が密集している地域です。その上(北側)は”青山百人組深地”と書かれた広大な敷地があり、護国寺前の通りまで崖線に沿った道が曲がりくねってある以外は道はなく現在とは全く違っています。目白通りから下(南側)は目白台上から神田川のある低地に下る坂道があり、大洗堰のあったすぐ上流、”駒塚橋”すぐ上に”胸突坂”がありますが、絵図では上流側に少しずれている道があり近江屋版にその坂道が”ム子ツキサカ”と書かれいますことと、水神社のある位置からこの坂道が”胸突坂”のある坂道であると思います。絵図ではその右(東側)に曲がりくねっている道が描かれていますが、これは今の”椿山荘”の中にある神田上水脇から目白通りへ抜ける道ではないかと思われます。”胸突坂”から”日無坂”までの間には一本の道が目白通りと神田上水脇の道を結んでいますが、坂名も坂の印”|||”もありませんが他の道や位置からして”幽霊坂”のある細い坂道ではと思われますが、定かではありません。”小布施坂”のある道は1761年に開かれたとありますが、絵図(尾張屋版も近江屋版も)には描かれていません。 |
| |
|
| |
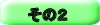 |
| |
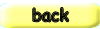 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|












































 江戸切絵図集成:尾張屋版「音羽繪圖」
江戸切絵図集成:尾張屋版「音羽繪圖」